どうも〜、ほやほやリサーチャーです!
実は色々と記事の下書きを書き溜めているんですが、まとまった内容を出すのってなかなか大変だなぁと思いまして。そこで、そうした記事とは別に、週報的な記事を書いていくことにしました。業務内容を具体的に書いていくというよりは、業務に関連して、あるいは全く関係なく、ぼやぼやと考えていたことを書き出していこうと思っております。
ということで、今週の振り返りです。
今週の振り返り:利用文脈って概念、伝わりづらいよな
利用文脈という概念は、まず意味合いが伝わらないし、さらにその重要性すらも伝わっていないのでは、という話です。
自分が携わっているUXリサーチは、探索寄りの内容であることが多いこともあってか「利用文脈」というワードが頻出します。しかし、協業しているデザイナーやエンジニアの方の様子を見ている限り、この概念はかなり伝わりづらいようです。
概念の意味理解は、雑に言うと「全然わからない」→「なんとなくわかる」→「しっかり理解した」というステップがあるように思います。利用文脈という概念は、自分が見ている限り「なんとなくわかる」ぐらいで止まってしまうことが多いようです。
振り返ってみると自分もそうでしたが(そしていまだに「しっかり理解した」と胸を張って言える感じはありませんが)、「利用文脈と言うぐらいだから、要するに利用時の文脈でしょ、だから、どういう流れでユーザーが対象物を利用しているか、みたいな感じじゃないの?」ぐらいの理解は割とすぐにできます。問題は、「どういう流れ」とは一体具体的になんなのか?ということを考えるのが意外と大変だということです。
そして、さらに重大な問題なのが、利用文脈という概念が理解されていないのは、その意味合いにおいて以上に、重要性においてではないかという話です。
あるサービスにおいて、利用文脈が決まらなければ、そのサービスのターゲットが本当にそのサービスを使うかどうかは判断できない、と思っています。これまでコンセプト評価に何回か携わりましたが、もしターゲットにインタビューをして、利用意欲を5段階評価で聞いた時に皆が「5で!」と答えていたとしても、それはインタビュー対象者が「なんとなく使いたいかも」と思っている以上の意味合いはないようです。それは、コンセプト段階ではまだサービスが具体としてあるわけではないので、対象者も抽象的に判断せざるを得ないからです。しかし、利用意欲というのは、そこで捨象されてしまうような、ごく具体的な状況とか、環境とか、その人のやりたいこととか、そういったものにこそ左右されるのではないでしょうか。
そこで、コンセプトを発想し検証する段階で重要になるのが利用文脈という概念なのだと理解しています。この重要さをうまく伝えていくにはどうしたらいいんでしょうね🤔

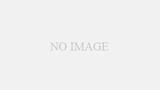
コメント